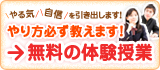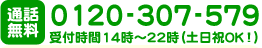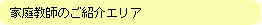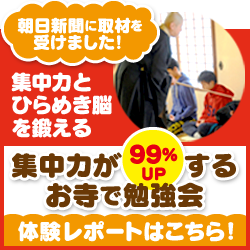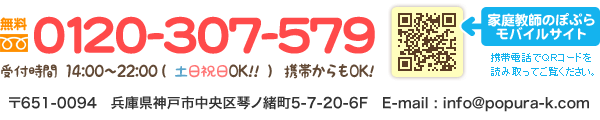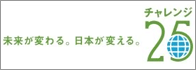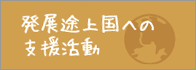体重チェックを知ろう毎朝起床時に体重を計ると疲労の回復状態や体調のチェックに役立ちます。
また、運動前後に体重を計ると運動中に汗などで失われた水分量が求められます。
体重の3%の水分が失われると運動能力や体温調節能力が低下しますので、
運動による体重減少が2%をこえないように水分を補給しましょう。
汗で体温調節皮膚には皮膚血管、温・冷受容器、あるいは汗腺など体温調節にとって重要な器官が存在しています。
血液は、体の中で発生した熱を移動し、皮膚血管の働きによって体の表面から放散(放熱)する熱量を調整し、
体温を調節しています。
運動によって熱産生量が増加したり、暑い環境によって体温が上昇して、熱放散の必要が増すと発汗がおこり、水分蒸発を盛んにして体温を下げる働きをします。汗でぬれた皮膚から蒸発する熱量は、体温や発汗量、
あるいは環境気温、湿度、風(気流)などの環境条件によって異なりますが、
100gの汗でおおむね1℃体温を低下させます。
汗は体温を調節するうえで、重要な役割を持っています。発汗能力は動物によって大きく異なりますが、
人がもっとも良く発達しています。人が砂漠などの暑い地域でも生活できるのは優れた発汗機能のおかげなのです。
汗の分泌体温調節に関係する汗腺は一般体表面に分布しているエックリン腺で、
その総数は200~500万といわれています。日本人では平均230万個の汗腺が体温の上昇に反応して汗を分泌
(能動汗腺)し、その汗腺の数は、2~3歳までに育った温度環境によって決定され、成人になってからは増加
しないともいわれています。
汗は汗腺から分泌され、その原液は血液(血漿)です。汗の主な成分としてはNa、Cl、KあるいはCaなどの無機成分のほかに、
ブドウ糖、乳酸などの有機成分が含まれます。その濃度は発汗量の多少や、暑さに対するなれ(暑熱順化)の程度によっても異なります。
分泌された汗のすべてが体温調節に有効に働くわけではありません。一部は体の表面から滴下し、また水滴のまま衣服や皮膚表面に
溜まります。気化して熱放散に有効に働く汗を有効発汗というのに対して、それ以外の汗を無効発汗といいます。
湿度が高いと有効発汗は減少し、無効発汗が増加しますので、体温が上昇しやすくなります。
夏のスポーツ活動は水分補給を十分に!スポーツのパフォーマンスの低下だけでなく、熱中症発生の危険性が高まります。
水分補給に十分心掛けたいものです。
- 2011年08月23日
- すたっふ日記
- admin